グリストラップ清掃とビル管法|オーナーが知っておくべき10の疑問
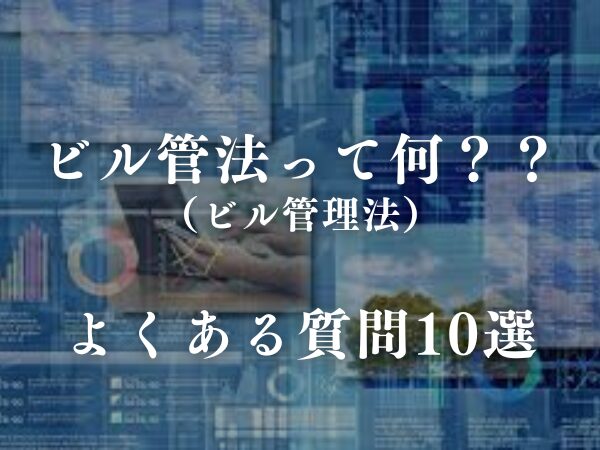
飲食店の衛生管理で避けて通れないのが「グリストラップ清掃」
一方で「ビル管法(建築物環境衛生管理基準)」という言葉を耳にして、
「うちは対象なの?」「罰則あるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、現場の管理者やオーナーからよく寄せられる疑問をもとに、
ビル管法とグリストラップ清掃の関係をQ&A形式でわかりやすく解説します。
また、ビルイン型飲食店で実際に5,000店舗以上で導入が進む「グリストラップ専用の洗剤」についても紹介します。
よくある疑問10選
グリストラップ清掃やビル管理法に関して、よくある質問をまとめました。
気になる項目をクリックすると、詳しい解説が開きます。
Q1. ビル管理法(建築物環境衛生管理基準)とは?
ビル管法とは、延床面積(建物のすべての階の床面積を合計したもの)3,000㎡以上の「特定建築物」に対して、建築物の環境衛生を維持するための基準を定めた法律です。
空気・水質・清掃などの衛生管理を定期的に行うことが義務づけられています。
Q2. 飲食店もビル管法の対象になるの?
基本的には「延床3,000㎡以上」の大型施設(ショッピングモール、商業ビルなど)に入っているテナントが対象です。
路面店や小規模店舗は直接の対象ではありませんが、衛生管理の指導対象(保健所・自治体)になるのが一般的です。
Q3. ビル管法を守らないとどうなる?
ビル管法は行政指導の性格が強く、違反した場合にすぐ刑事罰が科されるわけではありません。
しかし、厚生労働省や各都道府県の保健所による立入検査・改善命令の対象になります。
改善命令に従わない場合、
- 50万円以下の罰金
- 建築物環境衛生管理技術者の選任取消
- 営業停止や行政処分
などが科される可能性があります。
特に飲食店の場合は、悪臭・害虫・排水トラブルが発覚すると、
食品衛生法の観点からも営業に影響が出るケースがあります。
Q4. 誰が指導・監督しているの?
主に、都道府県または政令指定都市の保健所・環境衛生課が監督しています。
ビル管法は厚生労働省の管轄ですが、実際の立入検査や報告指導は自治体単位で行われます。
- 特定建築物 → 各自治体へ「管理状況報告書」を提出
- 清掃不備・悪臭苦情 → 保健所が立入指導
- 飲食店舗 → 食品衛生監視員(保健所職員)が現場確認
このように、現場レベルでは「保健所」が一番近い監督機関になります。
特にグリストラップに関しては、悪臭・害虫苦情がきっかけで指導が入るケースが多いです。
Q5. グリストラップ清掃はビル管法の中でどう扱われる?
ビル管法では「排水設備の管理」として扱われます。
油脂や残渣の堆積による配管詰まり・悪臭・害虫の発生を防ぐため、定期的な清掃が求められています。
Q6. 業者清掃は必要?自分たちで清掃するだけじゃダメ?
・業者清掃はグリスト内部を完全に洗浄し、堆積した油分や汚泥を専用車で回収します。
一回あたり1-3万円ほどで、月に1-2回の清掃が一般的です。配管の詰まると、メンテナンスと清掃で20万円以上ほどかかることも。
・一方で日常清掃は、表面のゴミ除去や油分の抑制を目的とします。
業務用洗剤はおよそ月に4,000〜8,000円程度になります。
どちらかだけでは悪臭や汚れを抑制することは難しいので、両方を併用するのが理想的です。
Q7.グリストラップはどんな洗剤で掃除すればいいの?
グリスト用洗剤は大きく分けて以下の3種類になります。
① 劇薬系洗剤(オキシクリーン・漂白剤など)
② 一般的なキッチン用洗剤
③ 分解系洗剤(酵素・微生物タイプ)
2025年、SNSでも話題の「分解系・酵素洗剤」は、実は劇薬洗剤よりも消臭力・安全性・環境配慮の点で優れていることが分かっています。分解によって油を“消す”のではなく“変える”ため、詰まりや悪臭の発生を根本から防ぐことができます。
SNSを中心に広がり、100店舗越えのラーメンチェーン店や五つ星のリゾートホテルでも導入されています。▶ 酵素系洗剤の詳しい仕組みはこちら
Q8. 保健所の立入検査ではどんなところを見られる?
保健所は、衛生管理・臭気・害虫対策・記録の4点を中心に確認します。
具体的には次のポイント:
- グリストラップ内の油の蓄積や浮遊物の状態
- 悪臭や虫の発生源になっていないか
- 清掃が定期的に実施されている証拠(清掃記録・日誌)
- 排水経路に詰まりや逆流がないか
指導が入るタイミングは、
・近隣からの悪臭苦情
・害虫(コバエなど)の発生報告
・厨房衛生状態の悪化 などが多いです。
軽度の場合は「改善指導」ですが、
繰り返すと改善命令や営業停止に発展することもあります。
Q9. グリストの汚れって普通に捨てちゃダメなの?
結論から言うと、ダメです。
グリストラップで回収した油や汚泥は、法律上「産業廃棄物」に分類されます。
一般ゴミと一緒に廃棄すると、廃棄物処理法違反になる可能性があります。
実際、自治体によっては不適切処理で罰金や指導を受けたケースもあります。
正しい処理方法は以下の3つ:
- 産業廃棄物収集運搬業者に委託して回収してもらう(数万円の費用発生)
- 水分を切って燃えるゴミに出せる固形物のみを処理
- 分解洗浄で油を排水基準を満たす水に変えて流す(酵素・微生物系洗剤の使用)
Q10. 清掃の頻度はどのくらいが理想?
清掃の頻度は、店の業種や油の使い方によって大きく変わります。
たとえばラーメン店や焼肉店のように油を多く使う場合は、毎日のゴミ取りに加えて週1〜2回の本清掃、月に1回以上清掃業者に依頼するのが一般的です。
一方で、カフェや定食屋など比較的油が少ない業種なら、月2回ほどの清掃、半年に1回程度の業者清掃が一般的です。
この違いが出る理由は、油の量・グリストラップのサイズ・水の流量にあります。
油は時間が経つと固まり、配管やグリストラップの内部の詰まりの原因になります。
油分の多く、サイズが小さく、水が多く流れる店舗ほど、汚れが溜まるスピードが早く、悪臭や詰まりのリスクも高まるため、清掃頻度を上げる必要があります。
また、清掃を怠ると保健所の立入検査で指導を受けることもあります。
悪臭が出てからでは遅いです。
「予防清掃」を意識することが、結果的にコスト削減とリスク回避につながります。
まとめ
ビル管理法は、建物の衛生環境を維持し、人の健康被害を防ぐために定められた法律です。
グリストラップの清掃はその一部であり、放置すると悪臭や害虫、配管詰まりの原因になるだけでなく、
最悪の場合は行政指導や営業停止のリスクもあります。
「衛生管理の基礎」として捉え、定期的な点検と清掃の記録を残し、油や汚泥を適切に処理することで、結果的に店舗全体の環境品質と信頼性を高めることにつながります。
是非参考にしてみてください。
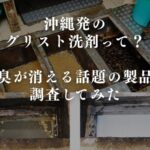


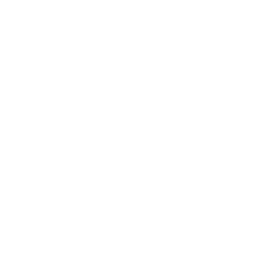
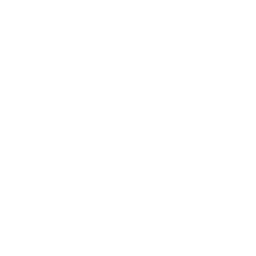
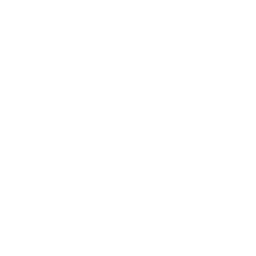
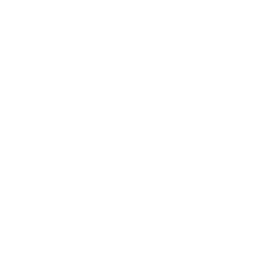
[…] ▶︎[グリストラップ清掃とビル管法|飲食オーナーが知っておくべき10の知識とは] […]